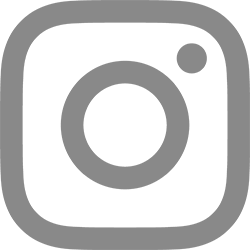活動報告
豊前小倉織研究会は、①小倉織の調査と研究 ②小倉織の制作 ③小倉織を広く伝える、の3つを柱にして活動しています。
工房展に向けて その2
2022.05.01
いよいよゴールデンウィークですね。準備も順調に進んでいます。帯反物のディスプレイなど全体の配置やバランスを考えながら行う作業もあれば、商品にプライスシールを貼ったり、展示コーナーに並べる小物づくりなど地道に黙々とする作業もあります。写真はメンバーが展示用のじんき作りをしているところです。じんきは、綿打ちした綿をハガキサイズほどにちぎり、細い棒を芯にして筒状に巻いたものです。皆ひたすら棒に巻いています(笑)。作品のプライスカードは、いつもは商品名と値段だけなのですが皆の遊び心に火がつき、こんなかわいいプライスカードになりました。 キューブやテトラの小さな箱は実際に織った布の写真を印刷した紙で作っています。 商品をご覧になる時に目に留めていただくと嬉しいです。(T子)
工房展に向けて
2022.04.25
5月6日からの工房展に向けて着々と準備が進んでいます。昨年から研究会メンバーも増え、機動力がパワーアップ! 工房2階はいつもは6台の機がひしめき、賑やかな機音が響いているのですが、今回は小倉織伝承会の会場づくりの為、他の機を部屋の奥に移動して、体験用の機1台とテーブルを手前に並べてワークショップのための空間を作りました。私たちにとってもこのような光景はめずらしく、楽しみながら進めています。また、大和代表制作の約2mほどのタペストリーをかけて空間を仕切り、その奥にスタッフの休憩所も作りました。なかなか素敵です!やさしい色合いの対のタペストリー、皆さんには何の模様に見えますか? お客様に楽しんでいただけるように精一杯準備を進めていきます。To Be Continued ♪(T子)***********今年は工房の路地の山芍薬がふたつ花を咲かせてくれました。研究会、伝承会,コラボ参加してくださる方々、工房展に向けてラストスパートです。(kei)
豊前小倉織研究会工房展2022 の開催のお知らせ
2022.04.16
5月6日(金)〜9日(月)10時〜17時まで「豊前小倉織研究会工房展2022」を小倉北区中津口にある工房で開催します。2015年、2017年、2019年(M展)に続いて4回目の工房展になります。今回は工房内を3つの会場に分けて、様々な企画を考えています。母家では、研究会の作品展示はもちろん、今まで取材を受けて記事が掲載された出版物を紹介するコーナーや作家の皆さんとコラボした素敵なアクセサリーや小物雑貨の販売、そしてこれから販売される商品(見てのお楽しみです☆)、小倉織の歴史資料の展示等々、皆さまがたくさん楽しめる展示を予定しています。工房1階では、繊維を使った様々な創作活動をする作家の集まりである「ITOBA」のお仲間の藍染作家クボマモルさんをゲストにお迎えし、藍染め・絞り作品の展示販売を行います。工房2階では、小倉織伝承会が作品展示の他、コースターや真田紐のワークショップをします。地元で育てた和綿を紡いで染め、織った優しい風合いの小倉織にぜひ見て、ふれてください。
感染対策には十分配慮が必要な時期ですので、会場の混み具合によっては少しお待ちいただくなどご不便をお掛けすることがあるかもしれませんが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
新緑の爽やかな頃、皆様のお越しを心よりお待ちしております。(T子) ※状況によりやむを得ず中止となる場合がありますので、お出かけの前にホームページでご確認頂きますようお願いいたします。
北九州市立すがお小学校授業「小倉織のことを知ろう」
2022.02.08
2022年1月27日(木) 9:45~11:20北九州市立すがお小学校において4年生児童7名に小倉織の授業を行いました。4年生の皆さんは普段の授業でも小倉織について学習しており、歴史の授業の時は先生のお話をとても真剣に聞きいていました。また、日頃から小学校の農場で綿の栽培をしていて、当日の朝も収穫した綿の実を手で綿と種に分ける作業をして持ってきてくれました。綿くり、弓打ち、糸紡ぎの体験の時は積極的に参加し、糸を紡ぐことの難しさや、紡げるようになった時の嬉しさを通して、昔の人の大変さを実感したようでした。コロナ禍での授業でしたが、子供たちの「楽しかった!」という声に、私たちもいっぱい元気をもらった一日でした。 (ゆう。/ こめ)
周望学舎「郷土の伝統文化小倉織」
2022.01.25
1月25日(火)10:00~12:00北九州市立年長者研修大学周望学舎に伺いました。講座のテーマは「郷土の伝統文化小倉織」。受講者は20名余で2時間の講義です。
まずは大和代表が小倉織との出会いや小倉織を織るようになったきっかけなどをお話しし、その後パワーポイントのスライドを見ていただきながら歴史や特徴などについて説明しました。皆さんとても熱心で講義中こちらからの問いかけにも積極的に答えられていました。特に盛り上がったのが実演の時間でした。綿繰り機を使って種と綿がきれいに分別される様子に「不思議だ!」、綿を丸めた「じんき」から糸が紡がれる様子に「う~ん、すごい!」など、綿繰りと糸車の周りにはあっという間に人だかりが出来ました。
質疑応答の時間では「藍は発酵するということだが毎日かき混ぜるのか」(A:天然発酵建てなので毎日かき混ぜます)「糸を染める度に藍は薄くなっていくのか」(A:藍の成分が減っていくのでだんだん薄くなります)などのお尋ねがありました。「男性用の帯はあるのか」(A:制作しております)という質問や「小倉織で一番向いているものは何ですか?」の質問に大和代表の「丈夫な布なので、帯を作っていますが、他にも向いているものがあったら私もそれ知りたいです(笑)」には教室中にどっと笑いが起こりました。最後に研究会の現在・今後の活動などを紹介して終わりました。
今回初めて周望学舎へ伺いましたが、皆さん本当にエネルギッシュな方ばかりで驚きました。年間を通しての受講や大学祭、修学旅行などもあるとの事で、充実した内容と皆さんの積極的な姿勢に一人納得してしまいました。(T子)
竹末市民センター 生涯学習市民講座「大人チャレンジ 小倉織を学び織ってみよう」
2022.01.21
1月21日(金)10:00~12:00今年初めての出張講座を竹末市民センターで行いました。密にならないよう配慮したため、参加者は10名と予定より少人数になりましたが20代から90代まで幅広い年齢層の方々が参加されました。初めに小倉織の袴や枝に付いた和綿などをお見せしながら小倉織の歴史や特徴を説明し、また、反物になるまでの過程を糸車や綿繰り機の実演を交えながらお話ししました。その後小さな織り機「mini小倉」を使って、いよいよ皆さまお待ちかねの織り体験です。予め糸をセットしたmini小倉の中からお好みの色やデザインのものを選んでいただき、早速織りのスタートです。紐の幅や糸の引き締め具合を確認しながら慎重に織る方や、コツをつかんで手早く織る方など皆さんご自分のペースで時間内に無事素敵な真田紐を織り上げました。ご参加くださった90代の方が楽しそうにテンポよく織られてる姿がとても印象的でした。織り上がった真田紐はストラップにして、チャームを付けて完成させてお持ち帰りいただきました。この講座は昨年開催の依頼があり、コロナ禍で何度も延期になった末、今年になってようやく実現しました。このような時だからこそ参加した方々の笑顔を見ることができて、本当によかったと感じた一日でした。皆さまありがとうございました。(T子)
今年もよろしくお願い申し上げます
2022.01.01
新しい年が始まりました。今年は様々なイベントやワークショップなどが予定されています。まだまだ気が抜けない状況ですが、感染対策を行いながら皆さまに小倉織の魅力をしっかりお伝えしていきたいと考えています。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。(T子)
小倉織縞の寅でご挨拶☆
新年のご挨拶・アクロス福岡イベントのご紹介
2022.01.01
新しい年が始まりました。本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
昨年は「北九州市民カレッジ-小倉織をまなび、織ってみよう」をはじめとする対外的な講座、イベントなどは中止や延期が多く残念な一年でした。
しかし、創作活動においては、小倉織を新しい用途に使う可能性が開けて刺激の多い一年でした。また、新たに3名の方々が研究会の活動に加わって下さって今までにも増して元気な研究会になっています。さらに、工房に集っている小倉織伝承会の方々ですが、年々技術の向上に加えて自主的な活動が生まれてきて、研究会を後押ししてくれています。地元の東谷に残された小倉織の布片の復元も伝承会の力によって実現して、今後の研究にも繋がって行きそうです。自然史・歴史博物館と協同で進めている小倉織の調査は、コロナの影響で遠距離の調査には行けない状況ですが、他の地域の研究者の方々との繋がりで日本各地に伝播していた「小倉織」の小倉以外の地域から見た姿が少しだけ分かってきた気がしています。今後も、小倉織がどこからやってきたのかというルーツ探しや、江戸期の小倉織の実物資料探しなどを続けて行く予定です。***********************************新年のイベントのご紹介です。アクロス福岡にて1月8日~10日まで、「お正月遊びと縁起物展」が開催されます***研究会は2F匠ギャラリーの縁起物販売会場に参加します。これまで手紡ぎの双糸で帯を織ってきて残っている糸を有効に使いたいと思っていました。なにしろ、綿を育て、種を取って綿打ち、糸に紡いで2本撚り合わせて染める・・・そんな手が掛かって大事な糸を少しでも捨てることは出来ません。今回その糸が「手紡双糸小倉織真田紐」に織り上げられてリールキーホルダーになりました。丈夫な真田紐です。1Fの会場では楽しいお正月遊びもたくさん体験できますよ。是非お越しください。(Kei)
「すてきにハンドメイド」発売中!
2021.11.30
9月に取材を受けたNHK「すてきにハンドメイド」テキスト12月号が発売されました。小倉南区で作っていただいている綿や工房の様子、制作作品、大和代表のインタビューと盛りだくさんの内容です。お近くの書店でぜひお手に取ってご覧ください!
🌻安心院より活動だより
2021.10.18
安心院在住の私は研究会工房へは月に1・2度行きますが、普段は大分県宇佐市安心院町の自宅で織っています。
周りは植物が多く、季節で様子が変わります。
最近では稲刈りも終盤に入り、慌ただしい音が聞こえてきます。
そしてこの時期といえば、セイタカアワダチソウが大家族でお目見えします。増えすぎると自滅する不思議な植物です。染めに使えて、さらに肌に良い成分があるので入浴剤としても使えます。花粉症の原因であるブタクサと間違われていますが、セイタカは花粉を飛ばさない無害な植物です。
煮始めは爽やかな良い香りです。
アルミ媒染で染め上がった色は、まろやかな黄色でした。外来種だから?かは分かりませんが、カリヤスや黄檗とは違う西洋な雰囲気を感じました。(わた子)