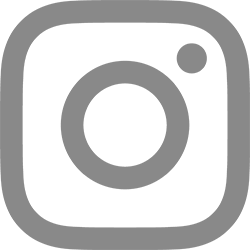NPO法人 抱撲 ワークショップ
2022.07.12
プランターで綿を育てている「抱撲」、3回目となるワークショップを開催しました。
まず、「小倉織」の歴史について簡単にふれたあと、実際に綿から糸になる過程を体験しました。
最初に綿から種を取り出す「綿繰り」、次に弓で綿の繊維をほぐし、最後に糸車を使っての糸紡ぎでした。
糸紡ぎは、なかなか大変でした。
そのあと自分の好きなデザインを選んでストラップ作りをしました。皆さん、暑い中、黙々と織り進めていました。
北九州市民カレッジ第4回「自分がデザインした縞のたて糸準備・mini小倉で真田紐を織る」
2022.07.09
まさかの6月中の梅雨明けですっかり夏の日射しの7月1日(金)市民カレッジ第4回が行われました。今回は、前回デザインした縞のたて糸を準備して、オリジナルの真田紐を織ります。まずは、たて糸をデザイン通りの順番に並べていく整経です。2人1組のペアで声を掛けあって色と本数を確認しながら、草木染めのかわいい糸玉を手の中で転がして整経台に掛けていきました。整経したたて糸を小さな織り機(mini小倉)に丁寧に一本一本通すと、受講生の皆さんが選んだ糸が綺麗な虹のように並びます。
いよいよ真田紐の織り始めです!たて糸は机と腰に結び付けた紐の間にぴんと張ります。これで、簡単な機の出来上がりです。たて糸が通してあるmini小倉を上げ下げして一段一段織っていくと、デザインしたとおりの模様が表れ、皆さんとても楽しそうに熱心に織っていらっしゃいました。最初は難しかった力加減などにも慣れて、どんどん織り進めているところで時間が来てしまい、続きはご自宅に持ち帰っての宿題となりました。
次回、出来上がった真田紐を見せていただくのを楽しみにしています♪ (こめ)
北九州市民カレッジ第3回「小倉織の縞の特徴を学ぶ・縞のデザイン」
2022.06.30
6月24日(金)市民カレッジ第3回が行われました。今回のテーマは縞のデザインです。
前回染色した7色を入れた17色から、第4回で織る真田紐の縞をデザインしていきました。前に並んだ草木染めの17色が遠目にも美しかったです。デザインをする前に、まずは小倉織の特徴を学びます。「武士の袴は小倉に限る」という言葉が残っているように、とても丈夫で糸にも他の織物とは違う特徴があります。経糸の密度が高いので縞模様が鮮明に出ます。講義の後はいよいよデザインタイム。まずは染めた糸を貼った染色糸データ票を作ります。その票を参考にしながら縞をデザインしていきます。幾通りにも広がる縞模様…途中煮詰まらないように、別室で糸車と高機を使った織り体験も行いました。この時間で仕上がらなかった方は宿題です。
黙々と、でも楽しそうに(デザインを生み出す悶絶もあり)第3回も無事に終わりました。(わた子)
北九州市民カレッジ第2回 「天然繊維触れる 染めについて学ぶ」
2022.06.19
6月3日(金)市民カレッジ第2回目が行われました。今回のテーマは染色です。受講生の皆さんは、まず初めに30分ほど、実際に天然繊維である麻や絹、ウール、木綿などの素材に触れながら、染色の仕組みや手順などを学びました。その後、実習室に移動し、濃い、中くらい、薄いの三段階の色の藍染め、茜染め、玉ねぎで黄染め、予め藍色に染めた糸に玉ねぎをかける緑染めの各チームに分かれていよいよ染色開始です。糸の染色は初めてという方が多いようでしたが、研究会メンバーのアドバイスを受けて、上手に糸を扱いながら染めていきます。空いた時間に他のチームの染めを見学したりしながら、染め方や色の違いに驚いたり、教室内は和気あいあいの空気に包まれていました。今回、皆さんの手で美しく染められた7色の糸は、しばらく衣桁にかけて乾くのを待ちます。次回は研究会で事前に染めた糸も加えた17色の糸で、おまちかねの真田紐のデザインです。たくさんの素敵なデザインが生まれるとよいですね。今からとても楽しみです。(T子)
北九州市立生涯学習センター主催 北九州市民カレッジ『小倉織を学び、織ってみよう』(全5回)が開講しました
2022.05.22
3年振り8回目の講座が、5月20日に始まりました。ありがたいことに今回も多数の申込みをいただき、抽選で20名の方が参加されています。 第1回目の詳しい様子は活動報告で紹介していますのでぜひご覧ください。
北九州市立生涯学習センター主催 北九州市民カレッジ『小倉織を学び、織ってみよう』(全5回)が開講しました
2022.05.21
3年振り8回目の講座が、5月20日に始まりました。ありがたいことに今回も多数の申込みをいただき、抽選で20名の方が参加されています。初回は「小倉織の歴史」の講義、綿繰り・弓打ち・糸紡ぎ・機織りの実技体験と盛沢山。豊前小倉織伝承会の皆さんにご協力頂き、緊張と期待の入り混じる中、無事に一日目を終えることが出来ました。私自身は、研究会会員として初めて参加しました。前日には2時間、糸紡ぎと説明の練習をして臨んだのですが・・・。当日は無我夢中。担当した受講生の方が、楽しんで頂けていれば嬉しいです。次回は「天然繊維に触れる、染めについて学ぶ」の講義と、糸の藍染め・草木染めの実習です。受講生のみなさま、5回続けてのご参加お待ちしています。〈Y子〉
工房展2022を終えて
2022.05.21
5月6日(金)~9日(月)に開催した工房展は、お陰様で天候にも恵まれ200名を超えるお客様にお越しいただき、無事終えることができました。本当にありがとうございました。会場となった豊前小倉織研究会の工房に初めて足を運んで下さった方もとても多く、作品や商品としての小倉織はもとより、日頃からの私達の活動について、実際に見て、触れて頂けたことが何よりうれしかったです。今回の工房展は多くの作家の方々や関係の皆様にご参加、ご協力いただいて実現いたしました。ゲスト参加の藍染め・絞りのクボマモル様。作品の美しさと模様の緻密さで、商品はあっという間に売切れ予約販売も! 私達スタッフも魅了されました。研究会の布を使ってすてきな商品にしてくださいました、Akoya.様、行武様、ITOHEN様、COEURDECOR(クールデコ)の森様、手縫い革職人Aile Bleue(エールブルー)の結城様、野上神仏具店様と、モノづくりの作家の方々の手によってワクワクするような新しい小倉織の世界が開けました。帯反物のディスプレイに必要な用具を快くお貸しいただきましたうめね呉服店様、皆さまに心よりお礼申し上げます。これからも研究会、伝承会一同、一生懸命活動を続けてまいります。4日間本当にありがとうございました。(T子)
豊前小倉織研究会工房展 2022
2022.05.09
6日(金)から開催された工房展も本日9日(月)無事に終了するかことができました。4日間、天候にも恵まれ、たくさんの方々に伝承会の取り組みを見ていただくことができました。「袴のことがよくわかった」「昔の縞が、素敵だった」などの感想をいただきました。また、キーホルダーやコースターの織りを体験した方々は、「楽しかった」「また、やりたい」などの声が聞かれました。今回初めて復元した布地でポシェット、額、ポケットティシュ入れ、アームバンド、アームカバーを作ってみました。昔から伝わる縞を身近に置いて使っていただきたいと思います。
工房展始まりました!
2022.05.06
2022年5月6日(金)〜5月9日(月)までの4日間行われます「豊前小倉織研究会工房展」が本日スタートしました!
小倉織の歴史を感じ、そして素敵な作品との出会い、小倉織を充分感じる事のできる空間になっています。共催の豊前小倉織伝承会、ゲスト参加のクボマモルさんの作品も見て楽しめる物ばかりです。本日は、沢山の方にお越し頂きました。「楽しかったです」「とてもいい作品が見れて良かったです」「素敵な小物ですね」と心温まる言葉を沢山頂いて、とても励みになりました。残り3日!まだまだ工房展は続きます!ご来場、お待ちしています。(ゆう。)
豊前小倉織研究会工房展 2022 始まる
2022.05.06
本日6日(金)より、9日(月)まで小倉北区中津口で工房展が開催されています。私たち伝承会も博物館に残る史料の復元など日々の活動を紹介したり、展示販売をしたりしています。「ミニ小倉」という腰機を使って織る真田紐のキーホルダーや、高機でコースターを織るワークショップも行っています。皆さんのご参加をお待ちしています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
月別一覧